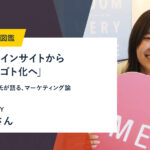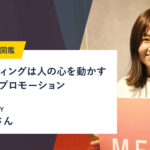Think differentキャンペーンから見るマーケティングメッセージの重要性
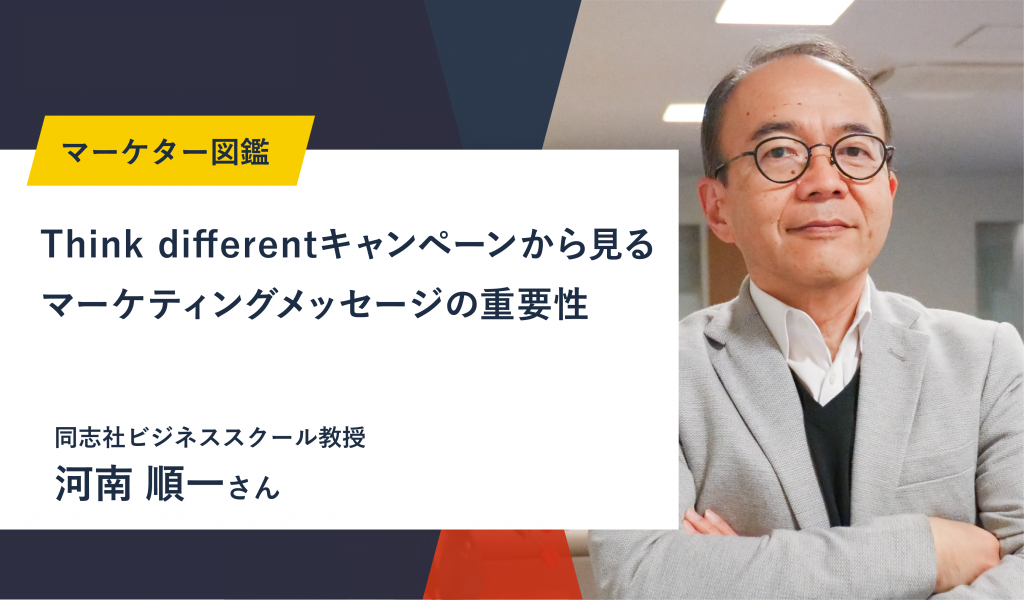
※本記事は2021年2月25日に公開した記事を再掲したものです。
同志社ビジネススクール教授の河南順一氏は、Appleが1997年にスタートした「Think different」キャンペーンの日本法人責任者を務め、マクドナルドではCEOコミュニケーションの一新を担った方です。
なぜAppleやマクドナルドは業績不振からV字回復できたのか、ユーザーインサイトに本当の意味で刺さる商品はどのように生まれたのでしょうか。そこにはマーケティングにおける重要なヒントが数多く散りばめられているはず。今回は河南さんに、マーケティングやユーザーインサイトの重要性、「Think different」キャンペーンの裏側など、じっくりお話いただきました。
目次
マーケティングをキャリアの軸にしようと決めていた
福田:まず簡単にご経歴を教えてください。
河南順一氏(以下、河南氏):最初に入社したのがモービル石油。ここでは営業やシステム部門に在籍していました。
11年ほど在籍したAppleや、サン・マイクロシステムズでマーケティングを担当し、その後マクドナルドに転職しました。基本的に、コミュニケーションは広告・広報・イベントなどの機能を持ち、マーケティングの中の一部門でしたが、日本で上場しているマクドナルドではコミュニケーションが別の部署に分かれています。最初はマーケティングを担当し、その後にコミュニケーション部門に異動しました。
8年ほど在籍した後、すかいらーくに転職。ここでは同社が再上場する際にコミュニケーション部門を立ち上げた後、2015年に再びマクドナルドに復帰。当時はマクドナルドの業績がかなり厳しかった時期で、CEOの社内外のコミュニケーションをメインにサポートしていました。マクドナルドは通算12年在籍していた形です。
福田:最初からマーケティング畑だったわけではないんですね。
河南氏:そうですね。ただ、もともとマーケティングには興味があり、自分のキャリアの主軸にしたいという思いがありました。
マーケティングと一口に言っても分野はさまざまですし、業界によっても手法は大きく異なりますが、共通しているのは「お客様のインサイトをしっかり掴む」こと。これはどこの業界、企業でも変わりません。
福田:Appleでの仕事について教えてください。
河南氏:Appleにはマーケターとして入社しました。Appleではマーケティングが幾つかの分野に分かれています。私が担当していたのはプロダクトマーケティング、マーケティング・コミュニケーション、サードパーティーマーケティングです。
当時のAppleはまだiPhoneが出る前で、パソコンの製造販売を主体とする会社でした。パソコンはアプリケーションや周辺機器があって、初めてソリューションとして売れるもの。ソリューションを売るために、サードパーティーの開発会社にApple用にアプリケーションソフトを開発してもらうよう依頼したり、プリンターやデジカメなどの周辺機器をつくるデベロッパーと一緒にマーケティングをやったりするのがサードパーティーマーケティングの仕事です。
福田:僕がぜひ伺いたいのは、Windows95が出てAppleが不調だった時期のことです。UIはMacとあまり変わらないのに、なぜ後発のWindows95が爆発的に売れたんだろうと思っていて。そのあたりの話をマーケティングの視点から伺いたいです。
河南氏:AppleのGUI(Graphical User Interface)はパーソナルコンピュータの操作性において圧倒的な優位性を誇っていたのですが、WindowsでGUIが実装され、Windows95で強化されたことで優位性は失われ、もともとビジネス市場でのシェアの大きかったPCの牙城を崩せなかったのが大きな原因だと考えてられています。なのでWindowsには、ビジネスユースのアプリケーションが豊富に揃っているんですね。デベロッパーにとってはシェアが大きいほうを優先するのはビジネス的に魅力があるので、どうしてもWindows向けの開発が優先されます。それでどんどん差が広がって行きました。
Apple復活の舞台裏
福田:その後Appleは復活に向けて動き出すわけですが、マーケティングの観点で何がポイントだったんですか?
河南氏:スティーブ・ジョブズ氏がAppleに復帰して最初にやったのが、パーソナルコンピュータ以外の製品にも多岐にわたって拡大していたビジネスを、再度フォーカスし直すことでした。
当時はプリンターやインクジェット、サーバー、ネットワークのコネクタ、モニターなどを扱っていましたが、それぞれが独立して分社化しており、全くと言っていいほどシナジーは生まれず、Appleとは何の会社なのか自分たち自身にも分からなくなっていて……。
Appleの優位性はどこにあるのかを整理して初めて、マーケティング戦略やコミュニケーションの軸を作ることができるんです。スティーブが大鉈を振るってビジネスを整理し、フォーカスする分野を絞ったのが、復活のきっかけになりました。
福田:具体的にはどんな風に進めたんですか?
河南氏:スティーブが復帰する前は発信するメッセージが世界各地の拠点や製品分野によってバラバラでしたが、復帰後にようやく全世界で統一したメッセージを出せる状態になりました。そのうえで、優位性だけでなく、Appleはそもそもどんな会社なのかをしっかり発信し始めたんです。
ビジネスユースではWindowsにシェアで差をつけられていましたが、印刷や音楽、グラフィックや建築など、クリエイティブに特化したプロ市場のソリューションには優位性があったので、そこにフォーカスを絞ってコミュニケーションを設計した形です。
その後大きく変わったのがiMacを出した1998年。当時は技術が分からないユーザーにもインターネットが広がり始める時期だったので、「若い人だけでなく、ご年配の方やお子さんでも使えるというメッセージとして「簡単・3ステップで使える」を打ち出しました。もともとパソコンユーザーではなかった層に大きく広げたのが、マーケティング的に大きなポイントでした。
デザインがファッショナブルだったので、展示先も秋葉原などにあるパソコンショップだけでなく、銀座や渋谷に広告を出したり、パソコンショップではない店のショーウィンドウに飾ったりしました。今までのパソコン業界にはない「ファッション性」を大きく打ち出すマーケティング戦略を取ったことも功を奏した形です。
福田:Apple製品の直感的な使いやすさは、社内でAppleがそもそも何の会社なのかがコンセプトとして共有されているからなのかもしれませんね。
河南氏:まさにそれがAppleの核になっていると言えます。Macintoshが出た際に作られたユーザインターフェースがずっと踏襲されており、これがAppleの使い勝手のベースになっているんです。ユーザーはパソコン側で何がどういう風に動いているのかを意識しなくても、ユーザーインターフェースが使いやすければ、自分のやりたいことができる。それが直感的な使いやすさにつながっているのです。
「Think different」で社内外にメッセージ届ける
福田:僕は「Think different」のキャンペーンが印象に残っているんですが、あのキャンペーンはどのように生まれたのか、どんな意味があったのか、振り返ってみていかがですか?
河南氏:最も意味があったのは、原点を忘れている人たちにAppleが何者なのかを思い起こさせたこと。その対象に社員も含まれていたのは大きなポイントです。
「Think different」のコピーで伝えたかったのは、世の中でクレイジーだと変人扱いされてきた人たちが世の中を変えてきた、というメッセージです。従来の考えにとらわれず、自分のやっていることにも変革を起こし世界を変えてきた人たち。そういうクリエイティブな発想を持つ人たちのためのツールをAppleが提供する――広告にはそんな一文を入れました。Appleは人間が持っているクリエイティビティを増幅させ、テクノロジーの力を使って、よりクリエイティブなものを実現する。それを支援する会社なんだと社内外に伝えたかったんです。
福田:広報は外向きの仕事だと思われがちですが、インナーブランディングも大事だったわけですね。
河南氏:何か新しいビジョンがあって、戦略を立てて実行する際、トップや戦略を考えている人たちだけでは会社は動きません。実際に動く社員が、そのビジョンや戦略をどこまで自分事化して展開していけるのかがポイントになります。
Appleもスティーブが復帰してガラリと戦略が変わったわけですが、何をどう目指していくのかを社員にきちんと理解してもらう必要がありました。ずっと倒産寸前だったので、社員の中には「Appleってもう駄目なんじゃないか」と思っている人もいたはずです。そこを根本的に変えたかった。まずは社員自身がマインドを変えないと、デベロッパーやユーザーには伝わりませんから。
コミュニケーションはインターナルも外に対しても、同じメッセージでなければなりません。Appleには熱狂的なユーザーも多く、「Think different」は彼らにかなり響きました。ただ、彼らはマジョリティではなくイノベーターなので、熱狂的なユーザー以外にも広げていく必要がありました。
社内でもスティーブ・ジョブズ氏のカリスマ的なところに惹かれた社員にはしっかり響くんですが、そうではない人もいるわけです。彼らにもしっかりメッセージを浸透させるよう意識して、コミュニケーションを設計しました。
会社が変わってもユーザーインサイトの重要性は変わらない
福田:マクドナルドや他の会社では、どのようにユーザーに向き合ってこられたんですか?
河南氏:業界や製品は違いますが、インサイトを掴む部分では同じですね。例えば2006〜2007年にスタートしたメガマックという商品が出た当時は、健康志向の風潮が強かったんです。ガッツリ系でカロリーも高いから反発がありそうだ、まずはメディアから叩かれるのでは、とマーケティング部門は考えるわけです。
そこでインサイトの話になるんですが、マクドナルドのインサイトは何だと思いますか? お客様のアンケートやリサーチを取ってみると、マクドナルドはヘビーだからヘルシーな商品がほしいという意見が出ます。でも野菜をメインに打ち出した商品を出しても、あまり売れていなかったんですよ。ではお客様のインサイトはどこにあるのか。
アンケートには「野菜系の商品がほしい」と答えても実際には行かないという女性のお客様にヒアリングしてみると、「サラダや野菜を食べるためにマクドナルドには行かない」って(笑)。で、お客様のインサイトを掘り下げていくと、マクドナルドが好きな理由は野菜やヘルシーさとは別のところにあることが分かったんです。
フォーカスグループインタビューなどを行うと、マクドナルドに対するイメージとして「ジャンク」という言葉が必ず出てきます。でもそこを掘り下げていくと、ジャンクという言葉はネガティブですが、その味が好きなんだと分かる。ヘルシーを求める風潮によって抵抗感はあるかもしれないけど、マクドナルドが好きなお客様に響かせるためには、その掘り下げた部分を打ち出す必要があると考えたんです。結果的にメガマックは私たちの予想を遥かに超える反響がありました。インサイトの掘り下げの重要さを感じる経験でしたね。
福田:2006年に発売された「サラダマック」は販売が振るわず、その後で出たメガマックが大ヒットしたのは、ユーザーインサイトを考える事例としてすごく分かりやすいですよね。
Appleも含め、成功している企業やプロダクトも、やはりユーザーの表層化・顕在化したニーズより、深層心理にあるようなものを探っているのだなと再認識しました。
河南氏:そうですね。もちろんお客様の潜在ニーズを商品に反映する姿勢も持っていなければならないし、実際にサラダマックのように商品としても出しますが、需要予測を見誤らないようにしないと大変なことになります。